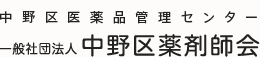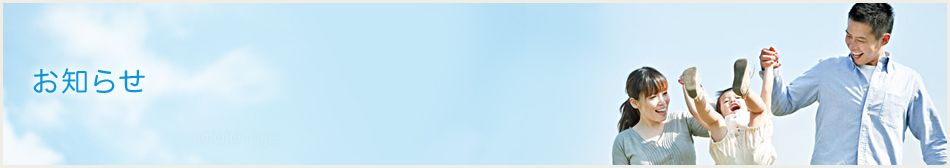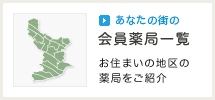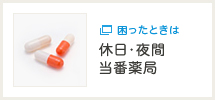平成24年2月 学術講習会「わが国で発生した薬害事件の経緯と医薬品情報学のすすめ」
平成24年2月8日中野サンプラザにて、学術特別講演会として千葉大学名誉教授山崎幹夫先生に「わが国で発生した薬害事件の経緯と医薬品情報学のすすめ」というテーマで講演していただきました。その一部を紹介します。
1.わが国における薬学のはじまり 日本の薬の歴史
奈良・平安期 552年 仏教伝来 体系的中国(漢方)医学の導入(536年ともいう)
701年 大宝律令 律令下「薬師(くすし)」は官職として医療を担当
鎌倉期 1192年~ 医師は武家、大名に抱えられ、在野開業医師も出現
室町期 1338年~ 寺院製剤(配合薬)の商品化と販売―売薬
江戸期 1603年~ 藩許製剤(「富山の反魂丹」等)、家伝、秘伝薬などの製造と販売。
オランダ医学(蘭学)の導入
明治期 1868年~ ドイツ医学の導入 漢方医学を否認 「売薬取締規則」政府による許可制始まる
官許売薬第1号は東京池之端守田治兵衛の「宝丹」「薬律」制定
近代医薬品(医療用医薬品)の輸入と国内生産開始
近代~現代 「薬律」から「薬事法」制定へ 売薬は近代薬学の導入にともない家庭薬、
大衆薬、一般薬、市販薬、OTC薬、一般用医薬品という名の変遷
を経て現代薬への道を歩んだ

2.“薬害事件”の発生
①サリドマイド
1957年にグリュネンタール社(ドイツ)から睡眠薬コンテルガンとして発売。
もともとはてんかん患者の抗てんかん薬として開発されたが効果は認められず、その代わりにその催眠性が認められた為、睡眠薬として発売された。
しかし、1961年頃から副作用として四肢の発育不全を引き起こし手足が極端に未発達な状態で出産、発育するといったことが報告され、大きな問題となった。
当初、副作用も少なく安全な薬と宣伝されたことから妊婦のつわりや不眠の改善に多用され、後の被害拡大につながった。
日本では1958年大日本製薬が「イソミン」の商品名で販売開始。翌年には胃腸薬「プロバンM」にサリドマイドを配合し販売。妊婦のつわり防止に使われた。
1962年5月に製品の出荷を停止したが、その後4ヶ月程回収はしなかった為、しばらく市中に出回り被害は増加した。全世界での被害者はおよそ5800人と言われている。しかしサリドマイドは催眠作用以外にも様々な薬理作用を持つことがわかって見直しの声が高まり、現在はアメリカ等でハンセン病治療薬として、また多発性骨髄腫治療薬などとしても販売が再開されている。日本でも2008年10月厚生労働省は、多発性骨髄腫の治療薬としてサリドマイドの製造販売を承認した。
②ソリブジン
1979年ヤマサ醤油により合成され、1993年9月3日日本商事により販売された抗ウイルス薬。商品名ユースビル。9月19日に死亡第一例、市販直後1ヶ月に死亡14例発生。11月19日出荷停止、回収を発表。FU系薬剤との併用により、FU系薬剤の代謝が阻害され、血中濃度が上がり血液障害が引き起こされた。これは構造式からも予測可能であり、防げる薬害事件であった(実験動物でのデータは1986年に得られていた)。
③チクロピジン
1981年第一製薬より発売。商品名パナルジンなど。この薬剤は、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)、無顆粒球症、および重篤な肝障害という重大な副作用が発現することが知られている。これらの重い副作用はその約9割が投与開始後2月以内に発現しており、本医薬品投与開始2ヶ月間、2週に1回の定期的検査(血液、肝機能)を行うことで、これら副作用の早期発見、重篤化の防止が可能である。しかし、使用開始後2ケ月間は2週間に1度は血液検査を行うべきであるとされていたが、この警告を忠実に守った医師は1/4に過ぎなかった。また、日本での重篤な副作用の発生率は欧米に比べ非常に高く、日本人に多い特有のHLAと相関を示すことがわかった。(HLA:ヒト白血球型抗原)
3.医薬品の安全対策
医薬品の適正使用
(1)的確な診断に基づき患者の状態にかなった最適の薬剤、剤形、適切な方法・用量の決定
(2)調剤 (3)患者への薬剤についての説明と十分な理解(4)正確な使用 (5)効果や副作用の評価 (6)処方へのフィードバック市販後調査制度(2001年10月1日より制度として実施)
新医薬品の販売開始直後の副作用等の被害を最小に止めることを目的とし、製造業者は新医薬品の販売後6ケ月間、全医療機関に対し確実な情報の提供、注意喚起等を行い適正使用に関する理解を促すとともに重篤な副作用、感染症の情報を迅速に収集し必要な安全対策を実施する。
4.医療の安全を目指す新しい薬学教育のはじまり
これまでの物質だけを対象とした薬学からヒトを対象とする薬物治療に直結する薬学へ。
「医薬品情報学の教育は、医薬品の適正使用に必要な医薬品情報を理解し正しく取り扱うことができるようになる為に、医薬品情報の収集、評価、加工、提供、管理に関する基本的知識、技能、態度を学習する」医薬品情報は ①良い薬を作る(創薬:製薬企業)②正しく使う(適正使用:医療現場)③上手に育てる(育薬:行政・医療・製薬現場)の全てにそれぞれの立場から関与する。